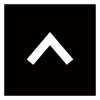立て矢結び
2020.09.12
立て矢結びとは、江戸時代、武家や大名家、将軍家で務めていた御殿女中が締めていた帯の結び方です。
237ssam-407x600.jpg)
時代劇や志村けんさんのコントにでてくる女性によく見られますね。
実は、この女中の姿が、花嫁さまの「引き振袖」姿のルーツです。
江戸時代、御殿女中の仕事は町民女性にとっては憧れの職業だったので、
女性たちはその姿を自分の「祝言(結婚式)」の装いに真似をしたのが始まりだったと言われています。
また、当時の引き振袖は、袂(たもと、袖)の下の部分だけに柄があるのが一般的で、
その後、袂の下の部分を断って「留袖」にしたと言われています。
「留袖」は、「袂を切り留めた」ということから名付けられたという言い伝えもあります。
そんな「立て矢結び」ですが、女中の位によって、
位の高い女中は豪華な織の帯を、
下のものは「黒繻子(黒無地で今でいうサテンの一種)」を締めていました。
また、結びの向きも、
屋敷内では右上、屋外では左上 といったように結び分けていました。
では、なぜ結び分けていたかというと、諸説ありますが、
■当時の女中は護身用に左に剣をさしていて、戦う時に帯の結びが邪魔にならない様に左上にしていた。
■逆に屋敷内にいるときは、戦意はありません・・という意思表示に右上にしていた。
■屋敷内姿、屋外姿を決めることによって、逃げ出さない様に、秘密をばらまかないように、むやみに外出できないようにした。
などなど・・
いずれにしても、女性の活動を縛っていた・・という時代ですね。
振袖は、その帯結びが、打掛姿や他の和装姿と違い魅力的な箇所となります。
花嫁さまの「引き振袖」は古典的で格調高い「立て矢結び」が多いですが、
現在では、華やかで格調高く見せることを第一に考えて、様々な結び方をしています。






我社でも、着物やヘアメイク、季節やロケーションに合わせ、格調高く華やかな帯結びの「引き振袖姿の花嫁さま」をご提案しております。
前撮りでは圧倒的に「打掛姿」が多いですが、個性的で華やかな「引き振袖姿」もお勧めです!
(株)北徳 代表 鎌田啓友記
■ 前撮り・和装なら、北徳|名古屋
→『北徳ホームページ』
『和装にこだわりたい』そんな想いにお応えします!歌舞伎や日本舞踊の『舞台衣裳』を扱う会社です。他では見かけない衣装が豊富。婚礼前撮りでは王道の花嫁姿・花婿姿で撮影ができます。業界では珍しい老舗衣裳店。創業 慶応元年(1865年)伝統を継承する 名古屋 北徳です。
■ Instagram
→『北徳スタッフ』(スタッフの日々徒然)
→『北徳ギャラリー』(お客様写真)
■ amebaブログ
→『アメーバブログ』
■ お問い合わせ等
→『お問い合わせ・ご予約について』
→『アクセス』(Googleマップ)
カテゴリ
アーカイブ
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月